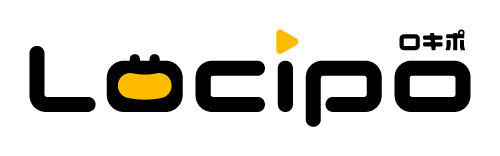子どもの不登校|年齢別の傾向と関わる要因・周りの対応【小児科医解説】
子どもの不登校はどうして起こるのでしょうか。その要因にはさまざまあり、年齢によっても傾向が変わるそうです。今回は、子どもの不登校に詳しい小児科医に、不登校に関わる主な要因のほか、医師や周りの大人の関わり方について聞きました。
 | 長崎県立こども医療福祉センター所長 小柳憲司(こやなぎ・けんし) 専門は小児科学、心身医学。長崎大学医学部・教育学部、佐賀大学医学部、長崎医療技術専門学校非常勤講師なども務める。書籍 「白ひげ先生の幸せカルテ ココロちゃんの記録」 監修。 |
※この記事は、中部電力が運営する子育て情報メディア「きずなネットよみものWeb」に掲載された記事を転載したものです。
子どもの不登校の要因
子どもの不登校がたびたび問題になる中で、私の勤務する病院にも学校に行けなくなった子が多く訪れています。「どうして学校に行きたくないの?」と聞くと、ほとんどの子が「分からない」と答えます。明確に理由を答えられる子の方が、少ないといえるでしょう。
このような場合、子どもといろいろな話をしながら、「恐らくこういうことが関係しているのではないかな」ということを推測していきます。その子が不登校に至る「物語」を考えてみるのです。
これまで多くの子どもたちを見てきて、学校に行けなくなる主な要因には次のようなものがあると感じます。
〈小学校低学年の不登校の主な要因〉
・衝動コントロール困難
神経発達症(知的能力障害、自閉スペクトラム症、ADHD)など
・強い不安と緊張
分離不安症、場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)など
・家庭の問題
家族の精神疾患、生活習慣など
小学校低学年の場合、ADHD(注意欠如・多動症)や自閉スペクトラム症、知的能力障害といった発達特性が関わり、座って授業を受けられない子が少なくありません。
このようなケースは特別学級や支援センターに通うなど、環境を整備するほか、投薬治療で症状を抑えることも可能です。症状が気になる場合、まずは医療機関での検査をおすすめします。
〈小学校高学年~中学生の不登校の主な要因〉
・学習困難
勉強の遅れなど
・思春期の体調不良
起立性調節障害、頭痛など
・友だち関係のトラブル
いじめ、仲間外れなど
小学校高学年~中学生の場合は、学校の勉強についていけなかったり、体調不良や友だち関係のトラブルに悩んでいたりするケースが多いようです。
いじめが理由であるならば、学校に行かないという選択肢も必要でしょう。ただし、いじめられている「気がする」という場合には、しっかり話を聞いて検証する必要があります。周りの子が自分のうわさ話をしているように感じたり、友だちの騒ぎ声が苦痛だったり、本人の過敏さ関係したりして学校に行けなくなっていることも少なくありません。
そして、このようなストレスが重なると、起立性調節障害(自律神経がうまく働かないことによって起こる体の不調)などを発症しやすくなります。起立性調節障害で体調不良があったり、朝起きられなくなったりすると、ますます登校できなくなるという悪循環に陥ってしまいます。「ニワトリが先か、卵が先か」の話ではありますが、不登校というのは、さまざまな問題が複合的に絡んでいることが多いといえるでしょう。
〈高校生以上の不登校の主な要因 〉
・進路選択のミスマッチ
・学習量の増加による抑うつ・睡眠不足
・精神疾患の発症(統合失調症など)
高校生の場合は、自分のレベルより高い学校を選んだことで授業についていけなかったり、学校の課題が多すぎて睡眠不足になったりすることが関係する場合があります。適度に手が抜ければいいのですが、真面目に取り組んで頑張ってしまう子どもほどストレスを抱えてしまうことになります。他にも、高校生くらいになると、精神疾患を発症して学校に行けなくなるケースもあります。
不登校に関わる因子
不登校には、次のような生物学的因子(子どもの問題)と環境因子(学校や家庭の問題)が関わっています。
※小柳医師の話をもとにきずなネットよみものWeb編集部で作成
さらに、ここに子ども自身のストレス耐性も絡み合い、これらが複合的に作用しています。
※小柳医師の話をもとにきずなネットよみものWeb編集部で作成
例えば、大雨が降ると、川の水があふれ、洪水が起こってしまいますよね。しかし、上の図のように、強い雨が降っても、高い堤防があれば洪水は起きません。また、溢れる前にうまく放水することができれば洪水を防ぐことができます。ここで、雨の強さが環境因子(環境からのストレス)、堤防の高さが生物学的因子(生物学的因子を持っている場合、堤防が低くなる)、上手に放水できるかどうかがストレス耐性だといえます。つまり、いじめや両親の不和などの環境因子があっても、本人のストレス耐性や生物学的因子によっては、不登校に至らないケースもあるということです。
不登校というのは、「〇〇が原因だから、□□という治療すればいい」と、単純な因果関係で考えることはできません。広い視点で、どうすれば改善できるか、どのようなアプローチが可能かを考えていくことが必要です。
不登校に対する病院の対応
不登校を主訴として病院にやってくる子どもの多くが、学校に行けない理由の1つとして、「朝起きられなくて……」と言います。登校するのに気持ちの負担があれば、朝起きづらくなるのは当然ですが、起きられない要因として起立性調節障害(自律神経の機能不全によっておこる体の不調)が関係している場合もあるので注意が必要です。
そういった子どもには、まず何か病気が隠れていないかを確認します。病気が関係していれば薬を処方することもありますし、ゲームのやりすぎなどで生活習慣が乱れていれば、生活指導、睡眠衛生指導(質の良い睡眠をとるための行動・環境の調整)を行います。
その上で、学校に「行きたいけど、行けない」と訴える場合には、一緒に行ける方法を考えます。「行きたくない」という場合は、ずっと家に引きこもっているのはおすすめできませんから、短時間だけでも学校に行く方法や、教室に入るのが難しければ別室登校、学校に行くのが辛ければフリースクールなど別の場所で活動するなど、できることを考えていきます。
責めないで「受け入れる」
子どもはある日突然、不登校になるわけではありません。少しずつ学校に行くのを嫌がるようになり、だんだん行けない日があらわれ、その日数が増えていく……というようになります。
初期の段階で、親御さんが「どうして行きたくないのかな?」「頑張って行ってみようか」などと声をかけてみるのは有効です。ただし、無理やり学校へ連れていったり、「どうして行かないの!」と責めたりしてはいけません。学校に行かないことを責められると、子どもは余計外に出られなくなり、心を閉ざしてしまいます。
親子とも、現状が受け入れられずに混乱したり、不安になったりして、言い争いになってしまうことがあるかもしれません。そんなときには、家族が現状を「今は焦っても仕方がない」と受け入れると、子どもは徐々に落ち着きを取り戻していきます。
受け入れて「声をかける」
「学校に行けない自分」でも、家族から受け入れてもらえていると感じると、子どもは安心し、少しずつ元気を取り戻していきます。そして、家の中で落ちついて生活できるようになり十分な時間が経過すれば、子どもはだんだんと家の中にいるのが退屈に感じるようになります。
そんな時こそ、「外に出てみない?」「こんな場所があるらしいよ」という声かけのタイミングです。外に出て一歩を踏み出し、家族以外の人と関わる機会が増えると、子どもはどんどん元気になっていきます。
子どもの状況を受け入れるのは大切ですが、1番避けたいのは「何もしないで、そっとしておく」ことです。人は何もしないでじっとしていると、心も体も不調をきたしてしまいます。部屋から外に出るのが難しい場合は、「食事だけでも一緒に食べない?」と、声をかけるなど、できることから始めてみてください。
回復としてめざす地点は?
不登校を乗り越えた先のゴールは、「学校に戻る」ことに限りません。家に引きこもるのではなく、外に出て、社会と関わることさえできればいいのです。フリースクールでも、学習塾でも、放課後等デイサービスでもいいですし、中学を卒業しているお子さんならアルバイトでもいいでしょう。
大人になった時、社会の一員として生活していくためには「自分ができる範囲で、自分の役割を果たす」という意識が必要です。学校に行けなくても、家族の役に立つように、お手伝いをするのもいいでしょう。誰とも会わないでいると、人と関わるのが怖くなってしまいます。「家から出て、何かしてみようか」と伝えてみるのも1つです。
また、将来に向けて最低限の勉強をしておくことも忘れないようにしましょう。そんな風に未来に向けて少しずつ準備しながら、学校に限らずとも、本人が外に出て、動き始める日を待つようにします。
不登校に陥ったからといって、決して「お先真っ暗」なわけではありません。単に「学校に行けなくなった」「行かなくなった」だけです。それ以上でも以下でもありません。そのように考えた上で、将来へ向けて何ができるかを考えていくことが、最も大切だと思います。
文・聞き手:きずなネットよみものWeb編集部
この記事は、中部電力が運営する子育て情報メディア「きずなネットよみものWeb」に掲載された記事を転載したものです。