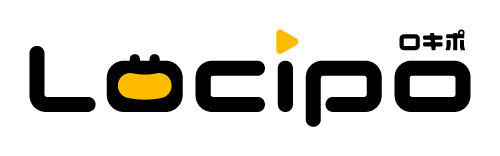「光洋陶器」陶磁器工場に密着!大人気ORIGAMIシリーズ「Aroma Mug」のこだわり
家庭の食卓を彩る陶磁器。今回取材班が向かったのは、岐阜・土岐市。土岐市を含む岐阜・東濃エリアは「美濃焼」の産地として知られ、国内の陶磁器の50パーセント以上を生産している、まさに日本一の産地。世界が絶賛する商品を作った「光洋陶器」の製造現場に密着した。
密着!コーヒーカップづくり 驚きのスゴ技マシン

「光洋陶器」
住宅街が広がる岐阜・土岐市内にある「光洋陶器」。ホテルやレストランで使われる業務用洋食器を手掛けており、年間200万個以上を製造している。
お皿やマグカップなど、取り扱っている食器は1万種類以上。

ORIGAMI「Aroma Mug」
今回紹介するのは、シリーズ全体で年間販売数約60万個を誇る人気商品、ORIGAMI「Aroma Mug」。底が広がっていることでコーヒーの香りが逃げにくいという。
早速、製造工程に密着! フォークリフトが運んでいるのは、陶磁器の原料となる粘土だ。工場では常時7種類ほどの土を常備、器の種類によって使い分けている。

「真空土練機」
座布団のような粘土が運ばれた先は、「真空土練機」というマシン。マシンに入れた粘土は、如意棒のようにグングン伸びていく。ずっしり重たそうな粘土は、ひび割れ防止のため、空気が入らないように練り上げられている。
お次はアームロボットが大活躍! ワイヤーでカットした粘土をリズミカルに積み重ねていく。
1本ずつセットした粘土をマシンがカット。カットされた粘土が、カップ1個分の量になる。
そして、カップの型に入れられた粘土に回転アームを押し付けると、粘土が型全体に広がり…
マシンがはみ出た粘土をカット! こうすることで、飲み口もすっきりと滑らかになる。
カットされた粘土は一カ所に集められ、原料として再利用されるそう。
成型後は乾燥させ、回転させながらスポンジで表面や飲み口を滑らかにする。
密着!コーヒーカップづくり 職人のスゴ技

原田パトリシアさん
カップに“持ち手”を付ける作業を担当するのは、原田パトリシアさん。この作業だけを10年間続けてきたエキスパートだ。
まずは持ち手に泥状の粘土を付ける。
持ち手はふにゃふにゃの状態だが、スゴ技でピタッと装着することができた。10年間で培った原田さんの技術は、この工場にとって欠かすことができない。
正確無比のスゴ技! 全ての取っ手が同じ位置に。「最初は難しかった。ハンドル(持ち手)が柔らかいから」と原田さん。

窯の全長は50メートル
いよいよ、最高800℃の熱でじっくりと「素焼き」していく。窯の全長は50メートルもあり、中央部分が最も高温。ゆっくり温度を上げ、ゆっくり下げることで、カップは割れることなくしっかりと固まる。
この窯に入ってから出てくるまで、なんと30時間! この手間暇が、高い品質を保つ胆になるのだ。
密着!コーヒーカップづくり 「光洋陶器」こだわりの焼き方
焼き上がったカップを待ち受けていたのは、黄色いアームマシン。一定のリズムで釉薬のプールに入れ、側面全体にまとわせたら引き揚げる。
陶磁器に欠かせない釉薬。色付けとして使う他、焼くとガラス質に変化するため、器の強度を高める効果がある。

ギリギリのライン!
驚くべきはマシンのスゴ技だ。カップの中に1滴たりとも釉薬が入らないギリギリのラインを狙い、側面だけきれいにまとわせている。こうした絶妙なタッチは、コンピューター制御のたまもの。このマシンは、生産効率の面でも必要不可欠だ。
釉薬をまとったカップは約1300℃の窯に入れられ、酸素を少なくした「還元焼成」という方法で焼かれる。これは、白い陶磁器をつくるのに向いている焼き方だそう。
窯に入れて約20時間待つと…やっと白亜のコーヒーカップが完成した。

さまざまなカラーバリエーションを展開
「光洋陶器」では、さまざまなカラーバリエーションを展開。カラフルな陶磁器は、酸素の多い状態で焼く「酸化焼成」という方法で、30時間かけてじっくりと焼き上げる。こうして色によって、2つの焼き方を使い分けていた。