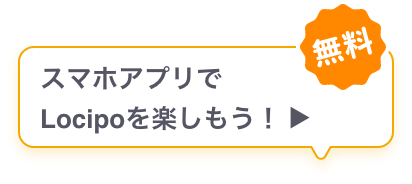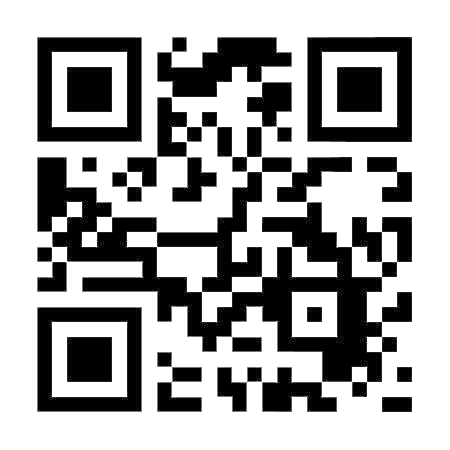【戦後80年】「話す必要ないと…」胸にしまった逃避行の“記憶” 90歳の女性が初めて手記に

シリーズでお伝えしている「戦後80年」。1945年の”戦争の終わり”は、少女にとって過酷な逃避行の始まりでした。 長年、胸にしまっていた記憶を形に残そうと、筆をとった女性がいます。

4冊のノートに、書き綴られた80年前の記憶――。
「母と弟と3人、抱き合って寒さをしのぎましたが、母の栄養のない乳では弟は泣くことも這うこともできず」
愛知県豊川市に住む、伊藤操さん、90歳。
「私の入学式。満州でね」(伊藤操さん)
“戦争の終わり”を、日本から遠く離れた「旧満州」で迎えました。
当時の記憶をたどり、手記を綴ったのは、去年のことです。
長年、家族に対しても、過去の体験を話すことをためらってきました。
「話したくないというよりか、話す必要がないと思いましたね。壊したくない。幸せに生きているというか、幸せでないかもしれないけど、平凡な生活で、一番いいんじゃないのと思うわけです」(伊藤さん)
穏やかで豊かな日々の運命が大きく揺らいだのは、終戦直前

伊藤さんがこれまで話して来なかった記憶――。
現在の中国東北部に位置する、旧満州。
1932年に、日本により「満州国」が建国され、“開拓政策”の一環で、多くの日本人が移住しました。
「レンガ造りのアパート、最初に行ったところ。冬になると氷の膜ができて、スケートができる。そこで大会があった」(伊藤さん)
穏やかで豊かな日々。しかし、運命が大きく揺らいだのは、1945年8月9日。
終戦直前に、ソ連軍が満州へ侵攻したのです。
父親は現地に残り、伊藤さんは、母と生まれたばかりの弟とともに、逃げることを余儀なくされました。
「青酸カリを渡され…」過酷な逃避行

そのとき、手渡されたものは――
「日本の軍人の嫁や子どもが『おかしな死に方をしてくれるな』と言われて、青酸カリを渡された。地獄ですよ。逃げる先々が、何にもないところに行くわけですもんね」(伊藤さん)
ソ連軍の機銃掃射を受けたり、身を寄せた先で、「自決」を促されたりした記憶も、手記にはつづられています。
「下の階にいた人が、青酸カリを飲んだと、見に行ったら本当に苦しんでいた。『あんなに苦しい思いをするなら、戦車にひかれたほうがいい』と言って、また戻って、隅っこで小さくなっていました」(伊藤さん)
逃げ続ける日々で。生後8カ月だった弟が衰弱し、息を引きとりました。
「穴がいっぱい掘ってあって、四角い穴が亡くなった人を埋める。大人でも子どもでも。ただ包んでね。持って行って、土をぽろぽろと、こぼしながら泣きました」(伊藤さん)
終戦から1年以上たち、伊藤さんは、命からがら母とともに、帰国しました。
「想像を絶する世界」伊藤さんの体験を次世代へ

80年もの間、胸にしまわれていた伊藤さんの体験を、次の世代に残そうとした人がいます。
鈴木みゆきさん、59歳。
鈴木さんが働いていた高齢者施設で、利用者の伊藤さんからノートに書かれた手記を見せてもらいました。
「小さい子が、すごいことを経験したんだなと、本当に読んだ時に泣けてきてしまった。操さんの思いをちゃんと読めるものにしてあげたい」(鈴木みゆきさん)
鈴木さんは、手書きの手記を多くの人が読めるように、パソコンで書き起こす作業に取りかかりました。
ノートに綴られた言葉を何度も読み、わからない部分を、伊藤さんに尋ねる。その作業は、戦争と向き合う時間でもありました。
「想像を絶する世界。苦しくなる。読んでいて、苦しくもなったので、本当にそんな時代がもう来ない方が良いと思い、残したいというのもありました」(鈴木さん)
80年心に封じ込めていた記憶を残した理由

完成した手記は、名古屋市の「戦争と平和の資料館 ピースあいち」に寄贈されました。
他の戦争体験者の手記とともに、冊子にまとめられ、年内にも販売される予定です。
忘れたい、でも、忘れられない――。
80年心に封じ込めていた記憶を残した理由。
「もちろん戦争はしちゃいかんよ。何の罪もない人を………ねぇ」(伊藤さん)