
"渡船の廃止"に存続を願う多くの人々の声 新大橋開通の陰で… 県営から市営に変更し存続へ 愛知県一宮市と岐阜県羽島市をつなぐ「中野の渡し」
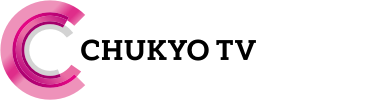
存続の灯は消えず―。

木曽川を渡り愛知県一宮市と岐阜県羽島市の間の約800メートルをつなぐ渡船「中野の渡し」は、新濃尾大橋が5月24日に開通すれば、その役割を終えて廃止されることが決まっていました。
しかし、一宮市、羽島市の両市民のほか、これまでに渡船を利用した人たちからの存続を願う声が多く、2026年3月まで愛知県が運営主体のまま運航されることがわかりました。
その後は、一宮市が渡船を引き取る決定がなされています。一宮市は現在、期間限定での渡船運航や、航路だけではなく木曽川の各所を巡る遊覧船といった利活用の方法を探っています。
一宮市公園緑地課の担当者によりますと、県と協議しながら、渡船をどのような形で存続していくのかを今年度中に決定するため、検討を進めているということです。
また、渡船は、愛知県では県道135号線(岐阜県は県道118号線)の一部としてこれまで扱われてきました。しかし、来年4月以降は一宮市の占用に変更されるため、市道への降格が決まっています。

中野の渡しは、1586年に岐阜県側にあった旧中野村が洪水で2つに分断され、往来するために船で渡るようになったのが始まりだといわれています。1938年に愛知県営となり、それ以来、愛知県が運営しています。
以前は木曽川の下流の至るところに渡船場がありましたが、1956年に濃尾大橋が完成した後、その下流に馬飼大橋が完成し、渡船の廃止が相次ぎました。
中野の渡しは現在、船外機を動力とし時速約18キロで走る第五中野丸1隻のみが運航しています。旅客の定員は12人。運賃は県道という扱いのため、無料です。
運航は月曜と木曜を運休とし、午前8時30分から午前11時30分までの3時間、午後0時30分から午後2時30分までの2時間、午後3時30分から午後4時30分までの1時間を営業時間としています。
乗務員は3人体制で、3人のうち2人が常駐する勤務形態をとっています。2025年5月時点で一宮出身の73歳と67歳の男性と稲沢出身の64歳の男性が船員として活躍しています。
この3年の利用者数は年間1500人以上で推移しており、24年の年間利用者数は2507人、23年は1800人、22年は1892人となっています。かつては通勤で日々利用する人々が多く年間に1万人以上の利用もあったそうですが、現在ではその面影は残っていないといいます。
現在の利用目的は観光のほか、自転車帯同での渡河、小学校の課外授業が主なものです。

乗船方法は、一宮市側から川を渡る場合には、待機小屋に常駐する船員に一声かけるだけ。一方、羽島市側から乗船する際は、合図用の旗を掲げて一宮市側に停泊している船を呼び寄せます。
船員の1人は「この仕事をしていてよかったことはなんですか?」との質問に対し、「アンケートを取った時、中野の渡しを残してほしいという声を聞いてうれしかったです」と話していました。






