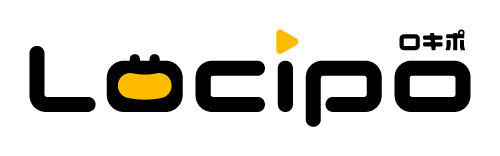半田市が誇る「亀崎潮干祭」に密着 巨大な山車に待ち受ける"激狭ロード"

半田市亀崎町の「潮干祭り」。
半田市亀崎町で最大のイベントであり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「亀崎潮干祭(しおひまつり)」。勇敢な男たちが豪華な山車を海にひき入れる光景は、まさに圧巻です。
山車の重さは4トンもあり、約80人がかりでひき回します。道中では、家や電柱に当たりそうなスリリングな場面も! 数々の“デンジャラスゾーン”が待ち受ける亀崎潮干祭に密着しました。
“動く美術品” 亀崎潮干祭に欠かせない巨大な山車

1865年に建造された山車「東組・宮本車」は、まさに動く美術品!
本番まで1カ月を切ると、街のいたるところで亀崎潮干祭の準備が行われます。今回密着するのは東組。巨大な山車は、釘を一切使わず、毎年イチから組み上げられていきます。
2024年で159歳を迎える東組の山車には豪華な装飾が施されています。最初に作られた時代でも高価なものでしたが、時代を経て彫刻や幕の刺しゅうも、今まで以上に価値が上昇。修復にはかなりの費用がかかるといいます。
亀崎潮干祭の山車に待ち受ける3つのデンジャラスソーン

東組の山車は、5輌のなかでも最も重量があるらしい。
山車が進むルートにはいくつものデンジャラスゾーンが! 1つ目は海岸の砂浜です。東組の山車は5輌の先頭であり、砂に埋もれれば祭りがストップしてしまいかねません。

怖すぎるギリギリの電柱の間を通り抜ける。
2つ目の難所が道の両側にそびえ立つ、2本の電柱。ぶつけることなく通り抜けられるのか?

狭い上に緩やかなカーブになっている難関ゾーン。
3つ目は、その道の先にある300メートルほど続く、最難関の激狭ロード! 1番狭いポイントは、道幅2メートルで、通過時の山車との隙間はわずか30センチになります。
山車の進行を指示する、祭りの花形「赤かんばん」。その役割と責任は超重大です。2024年に初めて、赤かんばんを務めるのは山内兄弟です。
デンジャラスゾーンを越える瞬間は胸アツ確定!

やーまいは「山側に引いて」という意味の掛け声。
祭り当日は重さ4トン、高さ5メートルの巨大な山車が、山内兄弟の掛け声で動き出します。まず2人の指示で向かったのは、亀崎潮干祭の最初の見せ場である海。1つ目のデンジャラスゾーンである砂浜に向かいます。真っ直ぐにしか回らない木の車輪、動力は人力のみ!

ほかの組の男衆が援軍として山車をひく、アツすぎる展開も!
なんと、砂浜に入った途端、急停止! 約80人の全力をもってしても、4トンの山車はピクリとも動きません。こうしている間にも、少しずつ潮が満ち、後ろの山車に影響が出てしまいます。
すると、ほかの組から援軍が来るという胸アツ展開が待っていました。組同士はライバルではなく仲間。男たちの力を結集し、見事砂浜を突破! 勢いそのままに波打ち際を突き進みます。

わずか30センチ! スレスレの電柱の間を見事にクリア。
浜へのひき下ろしを終え、巨大な山車が亀崎の町へ。そして、次なるデンジャラスゾーンであるダブル電柱に近づいていきます。
山車は木の車輪なのでまっすぐにしか進めません。そのため、赤かんばん・山内兄弟の舵取りが大事になります。そびえ立つ電柱に挑む、間隔わずか30センチ! 慎重に舵を切り、なんとかクリアしました。
最難関ポイント“激狭ロード”へ!

見るからにギリギリの戦いも、無事にクリアして歓喜!
しかし、ダブル電柱を通り抜けると、息つく暇もなく山車がギリギリ通れる道幅の、最難関ポイントの激狭ロードが待ち受けます。
山内兄弟の的確な指示で、山車が民家をすり抜けていき、残り約100メートル。最後の最後まで盛り上がりと、緊張感が入り混じる中、激狭ロードを通り抜けました。

いよいよ大詰め、5輌の山車が整列する熱狂と緊張の一瞬
しかしこれで終わりでなく、最後まで電線や連続するカーブを回避しながらゴールへと向かいます。5輌の山車がキレイに整列すれば無事終了。隙間なく山車を寄せるのも、赤かんばんの腕の見せ所です。
地域の結束力を感じる半田市の亀崎潮干祭。エネルギッシュかつ繊細な側面もある伝統的なお祭りに、観客は釘づけになっていました。