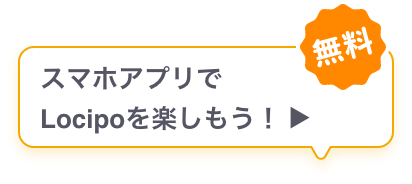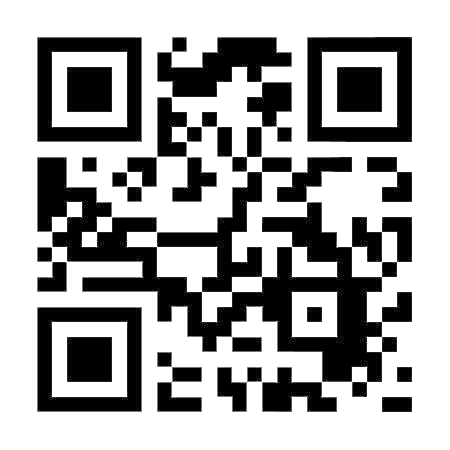シベリアで出会ったロシア人女性と“禁断の恋” 帰国後勤めた会社に激震が走った“モスクヴィッチ事件”【戦後80年 大石邦彦取材⑧】

これまで7回にわたり連載してきた「シベリア抑留記」。これは敵国でもあったロシア人女性、クリスタル・ターニャとの禁断の恋のエピソードでもある。
【写真を見る】シベリアで出会ったロシア人女性と“禁断の恋” 帰国後勤めた会社に激震が走った“モスクヴィッチ事件”【戦後80年 大石邦彦取材⑧】
戦後80年、自身もこれまで80年間封印してきた逸話というが、本人の許しを得て、ここに解禁する。知られざるシベリア抑留体験記として。
ターニャと別れを告げ、京都府の舞鶴港で日本の土を踏んだ長澤春男さん。当初は山形へ向かう予定だったが、迎えにきた兄がどうしても自宅へ寄って欲しいと懇願したため、名古屋へ帰った。しかし「本当は山形へ帰りたかった」と胸の内を明かしてくれた。
山形では「春男くん帰還おめでとう会」を開くため、住民総出でお祝いをする準備がされていたからだ。当時、シベリアからの帰還は、あの過酷な環境で耐え抜いて生きてきた大和魂を賞賛する風潮があった。それは、アメリカの傘下で新たな国の歩みを始めたことで、国民が忘れかけていた日本の精神性を思いださせてくれた出来事でもあったのだろう。
しかし、同時にアメリカ統治下で欧米流に染められていた日本では、捕虜とはいえソビエトで生活してきた春男さんら帰還兵は、共産主義者のアカのレッテルを貼られた。目に見えない偏見は、容赦なくシベリアの帰還兵を苦しめたというが、春男さんは意に介さなかった。
むしろ、シベリア抑留の経験を活かし、それをプラスにかえて人生を歩み始めたのだ。
「懐かしいなあ」帰国後3年間勤めた会社へ
帰国してまもなく、働き口を探し始めたのだが、自宅近くにあった自動車整備工場で勤務することになった。自動車整備は、抑留時代に培った知識、経験、スキルを存分に活かすことができたし、何より持ち前のバイタリティーで会社の中でも、自分の地位を築いていこうと懸命だった。
その工場で、意気投合した人物がいた。社長で創立者の佐藤鑛一氏だった。年齢は10ほど上だが、よくウマがあったのか、かわいがってもらった。
私は春男さんと共に佐藤自動車工場を訪ねた。本人にしてみれば、退社以来の訪問なのだから、75年ぶりくらいになるのだろう。
入社したものの、職を変えるまでの3年間の記憶。当時と同じ場所に、工場はかなり大きくなり、従業員も増えた元職場に足を踏み入れた。
すると、春男さんは「懐かしいなあ」と感嘆の声を上げながら、眼はキラキラと輝いていた。私が見ている風景とは、また違った風景が春男さんには見えているに違いなかった。
社長の佐藤鑛一郎氏が「ようこそ」と歓迎してくれた。創業113年の老舗企業の3代目、当時の社長の孫にあたる人物だった。
祖父の経営に抱いていた“ある疑問”
彼はおじいちゃんっ子だったらしく、祖父と同時代を生き抜いてきた予期せぬ訪問者に興味津々で、矢継早に質問を繰り返した。そして「祖父の顔を見てやって下さい」と写真を持ってきてくれた。
「うわ~、お久しぶりです」
春男さんは写真に向かって話しかけていた。ここから、春男さんの記憶が呼び覚まされると同時に、祖父の経営の疑問点の解明に向かっていくことになった。
当時の社長は、春男さんに会って話をしているうちに、その語学力に驚嘆したという。英語ならまだしも、ロシア語がペラペラなのだから。
シベリアで抑留されていた時に、言葉を必死になって覚えた事実を伝えると、さらに感心し、春男さんに興味を抱いていった。そして、何度か宴席を共にするうちに、社長はソビエトに興味を持ち、傾注していったのだ。
当時、ソビエトの客人が来た時は春男さんが通訳のようなことをしたこともあった。その後、春男さんは退職し、別の企業に勤めることになったのだが、佐藤自動車工場にとっての事件は、その後に起きた。
長年の時を経て…「やっと結びついた。だからか!」
自動車関連で創業100年を超える老舗企業、実はその前年に社史を編さんしていた。そこには創業時から今に至るまでの時代の流れから、変革する自動車産業の中で企業としていかに生き抜いてきたのかが、事細かに刻まれていた。
それを我々に見せながら、突然「やっと結びついた。だからか!」思いついたように声をあげた現社長は、社史のページを慌ててめくりながら、「この理由がわかりましたよ」と本を持ち、そのページを我々の目の近くまで移動させ、興奮気味に語りはじめた。
そこには「モスクヴィッチの大赤字」「モスクヴィッチ事件」と明記されている。話によれば、なぜか、当時の社長がソビエト連邦の車「モスクヴィッチ」に熱をあげ、それを大量に買い付けては輸入車として販売したのだという。当時は、自動車整備をしつつも、車の輸入販売も手がけていたという佐藤自動車工場、その輸入車の白羽の矢がソビエトの会社だったというのだ。
しかし、当時はアメリカ占領化の匂いが列島全体に漂い、敗戦国ニッポンは食もご飯からパンへ、魚食から肉食へ、生活も欧米化するなど、アメリカの色合いが濃くなっていた時代だった。今のような多様性は、まだ社会には存在せず、アメリカ化することが国是とされていた時代だった。
その時に、そのアメリカの最大のライバルで、当時東西冷戦の東側の象徴のソビエトに傾注するなど、数十年後に経営を任された孫からすれば、到底理解できない出来事でもあった。
会社に激震が走った“モスクヴィッチ事件”
「なぜ?ソビエトだったのか?」
社史を編さんしていても、いち経営者としても納得のいかない出来事だったゆえに、あえて「事件」としたのだという。
「俺の影響だよ、間違いなく」
それは、憶測などではなく、明らかに確信に近い言葉だった。現社長はまくし立てるように言った。
「当時の日本であれば、アメリカに占領され、アメリカ流に統治されていたわけだから、アメ車のフォードなどを輸入するなら理解できるけど、ソビエト車は…」
当時の社会情勢であれば「アカ」という誤解も招き、誹謗中傷が相次ぐなどして会社の存続が危ぶまれるかもしれない中での大きな賭けにでたということか。しかし、結果は売れた台数がわずか数台と惨敗。最終的には、大赤字となり、順調だった会社経営に激震を走らせた。それは単なる出来事ではなく、企業にとってはやはり事件だったのであろう。
現社長が、少し黄ばんだ時の流れを感じさせるアルバムを持ってきてくれた。それを開くと、そこには当時の先々代の社長がソビエトを訪れ、現地のロシア人と商談している写真が収められていた。
社長の顔は生き生きとしていて、これからの新時代の鉱脈を探しあてたような満足げな表情を浮かべていた。孫にあたる現社長には、とても優しかったという祖父。しかし、経営者としては全く理解できなかったソビエト車の購入の原点を知ることができたことが嬉しそうに見えた。
ただ、裏を返せば、春男さんとの出会いがなければ、会社は大きな痛手を受けることなく、経営も安定していたはず。2人の出会いは企業にとってプラスだったのか?マイナスだったのか?聞いた。
「紛れもなく、当社の最高齢のOBですよ」
「正解でしたよ。あの当時は失敗だったが、何事にも恐れず立ち向かうファイティングスピリッツが育まれたのではないか。それが今の社風につながっていますよ」
それは、本人に対する気遣いというより、心からの御礼にも見えた。最後に現役社員と記念撮影に臨んだ春男さん、脳裏には80年近く前の自分の姿がよぎっていたのかもしれない。社長に「紛れもなく、当社の最高齢のOBですよ」と言われ、「今日は来て良かった、良かった」と何度も口にしていた。
持ち前のバイタリティーでシベリア抑留時代を生き抜き、帰国しても尚、人生を切り開いてきた春男さん。どんな困難が立ちはだかろうとも、それを乗り越える強さと生きるヒントが詰まっているような気がした。
〈これまでの記事〉
・100歳抑留者が初めて明かす 戦後80年の秘密①
・ロシア人女性との“禁断の恋” 命つないだロシア語への執念②
・強制労働先での出会い「瞳は丸く大きかった」③
・忘れられない ターニャの「ボルシチ」④
・「ハルオ、私と一緒になって」 知る由もない祖国の状況・未練⑤
・2人に訪れる転機 忘れられない彼女の表情⑥
・彼女からの最後のプレゼントは“香水”だった⑦
【CBCテレビ論説室長 大石邦彦】