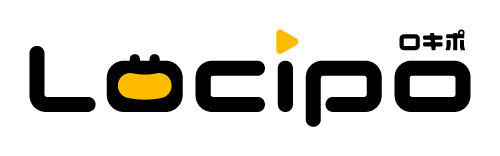ランナー必見のお役立ち情報も! やる気を引き出す!運動のコツ
この記事の動画のプレイリストはこちら!
“居座り寒波”も過ぎ去り、春の陽気を感じる時間が増え始める時期。街では、マラソンやウォーキングなどに取り組む人の姿が多く見え始めるなど、屋外で体を動かしやすい気候となりました。そこで今回は、スポーツを始める前に知っておきたい、“運動のコツ”を特集!元五輪選手が明かす現役時代のルーティーンや、健康科学の専門家が教える効果的なウォーキング方法など、明日の運動に取り入れたいをコツをたっぷりご紹介します。
元五輪選手がレース前のルーティーン公開!
野口みずきが大会直前に食べていたものとは?
元五輪選手の野口みずきさんと福士加代子さんが、大会直前に行っていた現役当時のルーティーンを紹介。
野口さんは、自分が今まで出場してきたレースで、成績が良かったときのゼッケンを集めており、大会当日に“お守り”として持参していたことを告白。そのお守りを忘れた時のレースは、成績が悪かったことを明かしました。
福士さんのルーティーンは、ラベンダーや柑橘類などのアロマオイルの香りで心を落ち着かせること。しかし、大会前はパニックのあまり、オイルの“原液”を手に乗せて直接吸引していたことを明かし、笑いを誘いました。
レースの5時間前に起きて、4時間前くらいに軽く動き、4時間前以降から食事をとり、2時間前に軽食をとっていたという野口さん。一方、福士さんはレース前などの食事は控えており、ゼリーを入れたドリンクを飲むことでエネルギーを補給。選手によって、レース前の食事の摂り方にも違いがあることにもふれました。
“大会前日はたらふく食べる”という野口さんが、一番食べていたものが「肉」。脂身が少なく、高タンパク質の鶏肉を食べていたといいます。
福士さんの前日の食事は、“うどん”や“ごはん“など「白物」が中心。野口さんは、元五輪選手・髙橋尚子さんの大会前日の食事も、“白物メニュー“だったことを話しました。
選手によって、大会前のルーティーンはさまざま。他、動画内では現役当時の勝負飯や他選手たちのルーティーンなども紹介しています。
パリオリンピックやマラソン、陸上の話題を発信する同シリーズ。他動画では、坂道の走り方や野口さんがランニング中に実際に聴いていた音楽リストなど、ランナー必見のお役立ち情報をたっぷり公開しています。
■番組情報■
東海テレビ「野口みずきのランナーズハイ」
大会直前は肉食う野口みずき!福士加代子がルーティーンをぶっちゃける!
2024年8月8日配信
お風呂上がりの10秒間で出来る!
「ランナーひざ」の対処法
骨や軟骨以外の原因で起こるひざ痛「ランナーひざ」。ランナーをはじめ、その痛みに悩まされた人もいるのでは。
ひざ治療専門医、『玉川病院』柳澤克昭先生が教えてくれたのは、自宅で簡単にできるランナーひざの対処法。柳澤先生によると、ランナーひざとは、別名「腸脛じん帯炎」と呼ばれており、主に長時間のランニングなどを行った際、おしりの筋肉から脛骨の上の方に繋がっているひざのじん帯「腸脛じん帯」が痛くなる疾患なのだそう。
ランニング動作で発症することが多いことから、“ランナーひざ”と呼ばれており、陸上競技者、ランニング初心者、下股(脚)の筋力が弱い人、下股(脚)の筋力が硬い人などがなりやすい傾向にあるといいます。
そんなランナーひざの対処法のひとつが、痛む箇所を10秒間押すこと。痛みがあっても躊躇せず、グッと押すことがポイントです。柳澤先生によると、お風呂上がりに1回3セット行うと効果的。痛みのある箇所をあえて押すことで、腱を和らげることを目的としているといいます。
柳澤先生曰く、「放っておくと慢性化して、治りにくくなることもある」というランナーひざ。発症したら安静を心がけ、その後は運動量を減らしたりするなど、じん帯に負担をかけないことがポイントだといいます。
動画内では、対処法を実践している様子や他対処法、ランナーひざの原因などもピックアップ。レース前やスポーツ中のセルフケアなどの参考にしてみては。
■番組情報■
CBCテレビ「健康カプセル!ゲンキの時間」
骨や軟骨以外が原因!?ランナーひざ
2023年6月25日配信
“1日2,500歩“で続けるコツ!
効果的なウォーキング方法とは?
健康科学を専門とする、『岐阜大学』春日 晃章教授が教えてくれたのは、“正しいウォーキング方法”。春日教授によると、習慣的なウォーキングで基礎代謝がアップすると、余分な脂肪の燃焼につながるほか、心肺機能も強化され、“健康な体作り”が期待できるといいます。
「ウォーキングは正しい歩き方をすれば、1日2,500歩ぐらいで健康の増進になる」と話す春日教授。効果的なウォーキングのポイントは、『上半身の肩甲骨を意識すること』、『歩くときはスターになりきる』の2つ。
上半身の肩甲骨を意識する際は、ひじを曲げながら腕を後ろに引くことがコツ。何度か動かして、肩甲骨の位置を確認します。そのまま腕の振りを縦にして、左右のタイミングをずらしていきます。しっかりと上半身を動かすことで、足への負荷を全身の筋肉に分散。運動効果アップを目指します。
歩くときは、春日教授曰く、「ハリウッドスターがレッドカーペットを威風堂々と歩く」ようなイメージ。背筋を伸ばし、あごを引き、視線は20m先に向けることがコツです。
他、動画内では足の正しい着地の仕方をはじめ、よりウォーキングの知識が深まる情報を紹介。手軽に日常に取り入れることができるスポーツ、ウォーキング。正しい歩き方を知って、日々のトレーニングに役立ててみては。
■番組情報■※
メ~テレ「ドデスカ+」
秋こそウォーキング!“1日2500歩”で続けるコツ
2023年10月17日放送
運動前のストレッチは大事!
アキレス腱はなぜ切れる?
人体で一番太い腱、アキレス腱。運動前のストレッチが欠かせない、体を動かすために大切な部分のひとつです。
重いものを持ち上げる強い筋肉と丈夫な骨、そのふたつを繋いでいるのが“腱”。アキレス腱は、ふくらはぎの筋肉とかかとの骨をつないでいます。
牛のアキレス腱を割いてみると、縦の繊維で強く結合していることが分かります。乾燥させた牛のアキレス腱は弓の弦に使われるなど、かなり丈夫な“アキレス腱”。
でんじろう先生が、乾燥した牛のアキレス腱にぶら下がってみても、まったく切れる気配がありません。しかし、このように丈夫なアキレス腱でも切れてしまうことがあります。それは、なぜなのでしょうか?
実はアキレス腱自体は伸び縮みせず、筋肉が伸び縮みしているからなのです。
でんじろう先生によると、人間の足の構造を見てみると、「指から足首までの長さ」と「足首からかかとまでの長さ」の比は2対1。そのため、つま先立ちをすると、てこの原理でアキレス腱は、体重の約2倍の力で引っ張られることになるといいます。
このように筋肉が伸びきった状態で、ジャンプなどをすることで、アキレス腱に無理な力がかかると、切れてしまうのです。
運動前に必要なストレッチ。健康な体でスポーツを楽しむためにも、ストレッチで筋肉をほぐし、アキレス腱に無理な力がかからないように予防しましょう。動画内で行われている、乾燥した牛のアキレス腱を起用したユニークな実験の様子にも注目です。
■番組情報■
中京テレビ「でんじろう先生のはぴエネ!」
アキレス腱はなぜ切れる?
2024年10月19日放送
スポーツがSDGsに繋がる!?
都市型スポーツ「アーバンスポーツ」の可能性
持続可能な社会を目指すSDGs。スポーツの世界では、その目標をスポーツの力で達成しようというチャレンジ「スポーツSDGs」にも関心が寄せられてます。
『大阪体育大学』学長・原田宗彦先生によると、「アーバンスポーツ」は、スポーツSDGsと相性の良いスポーツ。アーパンスポーツとは、東京オリンピックでも注目を集めた、若者に人気の都市型スポーツのこと。スケートボードやスポーツクライミング、BMXなどが例に挙げられます。
都市型のスポーツの魅力は、日常生活の延長で楽しめること。競技スポーツは特定の施設が必要になることが多いですが、都市型スポーツの場合、ストリートを使って身体を動かすことができます。
ファッションや音楽とも相性が良いため、スポーツに留まらない可能性も秘めているといいます。
スポーツと文化が結びつくことで、新たな“ライフスタイル”が誕生。その生き方に憧れる若者が増えることで、アーバンスポーツの力を使った“街づくり”につながるのです。
動画内では、スケートパークの建設をはじめ、都市型スポーツに期待できるスポーツSDGsへの効果など紹介。SDGsという観点で、これから始めるスポーツを選んでみるのも良いかもしれません。
■番組情報■
テレビ愛知「おしえてっ!原田センセイ!」
アーバンスポーツの可能性
2023年7月14日放送