【参院選/何で選ぶ?】「現金給付」か「消費減税」か…各政党の物価高対策 値上げ品目は去年の5倍以上に 専門家が指摘する「議論すべき点」とは?
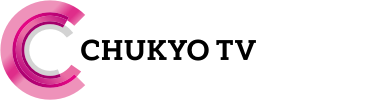
食料品から日用品まで値上げの波が押し寄せ、家計の負担は増すばかり。参院選を前に、各政党は「現金給付」と「消費減税」という二つの物価高対策を掲げていますが、専門家は「政策と同時に議論すべき点がある」と指摘。スーパーの買い物客や介護に向き合う高齢夫婦の声から、物価高対策の本質に迫ります。
市民が望む“物価高対策”は?「日本がよくなる持続型の案があれば」

名古屋市千種区のスーパー「サンエース 春岡店」。買い物をするたび、お客さんが感じていることは…。
70代:
「物価高で今月またいろんなものが値上がりした。なるべく買い物控えてまとめ買いして、あんまり来ないようにしようと思ってる」
50代:
「今まで買ってた嗜好品がちょっとずつ値上がりしてて、あまり買わなくなった」
止まらない物価の上昇。帝国データバンクによりますと、今年7月に値上げされる食品は2105品目。この数は、去年7月と比べて5倍以上と、大幅に増加しました。

物価高対策として各党で主張が分かれるのが「現金給付」か「消費減税」か。どちらがいいか、聞いてみると。
消費減税派 70代:
「絶対減税。給付ってばらまきでしょ。2万円なんてすぐなくなるし、あまりありがたくない」
現金給付派 80代:
「2万円給付金もらった方がいいんじゃないかなと思う。消費税なくなると(財源が)大変だと思う」

子育て中の女性は、子どもの食費が増え消費減税を望むものの、将来を考えるといきなりの廃止には抵抗も。
子どもが1歳9か月:
「子どもが大きくなる10年後20年後、日本がよりよくなる持続型の案があったら、そういう政党がいい」
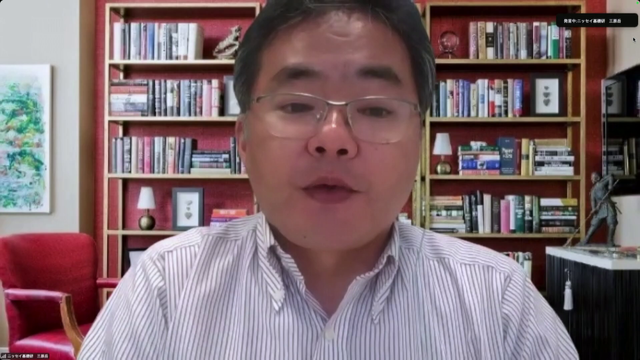
そんな「給付」か「減税」の議論。社会保障に詳しい専門家は、見落とされている視点があるのではと指摘します。
ニッセイ基礎研究所 三原岳さん:
「2012年に消費増税の時、社会保障目的で増税をすると決めた。消費減税をするということは、社会保障の財源が失われることになる」
現金給付? それとも消費減税? 80代夫婦が投票先を悩むワケ

愛知県内に住む80代の夫婦にも、ある不安が…。
愛知県春日井市内のデイサービス「てとりん村」で大道芸を披露しているのは、恋塚隆秀さん(84)。60歳で定年を迎えてからこの道に進み、今では月1回ほど介護施設などでパフォーマンスをしています。

施設の利用者が楽しんでいる中、最前列には妻・常子さん(83)の姿も。夫婦として連れ添って57年。11年前にアルツハイマー病と診断されました。
常子さんの介護度は最も重い要介護5。週6日のデイサービスや、週2回の訪問看護を利用しています。

身の回りの世話はすべて隆秀さん。ほとんど未経験だった料理もするようになりました。よく作るのは肉じゃが。常子さんが大好きな肉は、物価高の中でも惜しみません。
心がけているのは、とにかく優しく接することです。
そんな中、今、悩ましい思いをしているのが、「現金給付」か「消費減税」かの議論です。これまで社会保障の財源にもなっていた消費税。
恋塚隆秀さん(84):
「給付金なんか2万円もらっても仕方ない。介護用の(おむつや)パッドで月3万円ぐらい。僕は消費税下げてほしいけど(社会保障への影響が)あれば困るから、減税なしでも仕方ないかなと思う」

力仕事も求められる介護現場。大変さを知る身として、もう一つ心配なのは、介護スタッフのことです。
恋塚隆秀さん(84):
「とにかく(賃金が)安い。今、安いのに削ってでも減税するということであれば全く反対」
日本介護クラフトユニオンによると、去年7月の介護従事者の平均賃金は約26万5711円。一般的な平均賃金より6万4700円ほど低く、処遇の改善が課題とされています。
ニッセイ基礎研究所 三原岳さん:
「2024年度予算では、介護従事者の報酬に消費増税の一部を充てている。ただでさえ賃上げ財源が必要なのに、そこに消費減税をしたら、賃上げであてた財源をどうするんですかって話」

物価高対策だけでなく、財源についても議論の争点になりそうです。
恋塚隆秀さん(84):
「妻のためには何でもしてやろうと、お金が必要でも払える範囲はとにかくやってあげたい。社会保障の値上げは困ります」
対立する物価高対策 各政党の財源論に注目

今回の参院選では、与党が「現金給付」、野党は「消費減税」と、対立している構図の物価高対策。
野党の中でも、消費税を一律に減税するというスタンスの党と、食料品に限って減税するという党、給付と減税を一緒にやるべきだと訴える党と、意見に違いがあります。
ここで問題になってくるのが、財源はどうするのかというところです。
1人2万円の給付を訴える与党は、“3兆円台半ば”の予算が必要だといいますが、「自民」「公明」ともに、税収の上振れ分で賄うと主張。
給付と減税のどちらもやるべきという立場の「立憲」は、国の基金の余剰資金や、税制の見直しで捻出するとしています。
1人10万円の給付を掲げる「れいわ」は、まずは国債を発行して、これを実行した後、法人税率の引上げなどで対応していく考えです。
給付はせず、消費減税に特化するべきと主張する党では、「維新」は税収の上振れ、「国民」はそれに加えて予算の見直しで財源確保すると主張。「保守」は減税すれば経済成長でき、税収が増えるので賄えるとの考えです。
「共産」は法人税の引き上げ、「社民」は防衛費の引き下げなどで対応、「参政」は国内投資を促して経済成長につなげ、税収増で賄うとしています。
各党、さまざまな形での財源確保を主張していますが、物価高は楽になっても、別の形で影響が出てしまっては本末転倒です。
社会保障など、国民の暮らしを支えている予算を削らず実現することができるかどうかについても注目されます。






