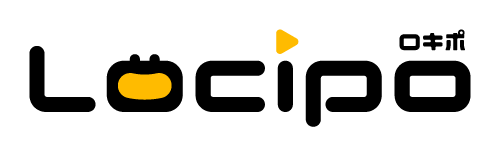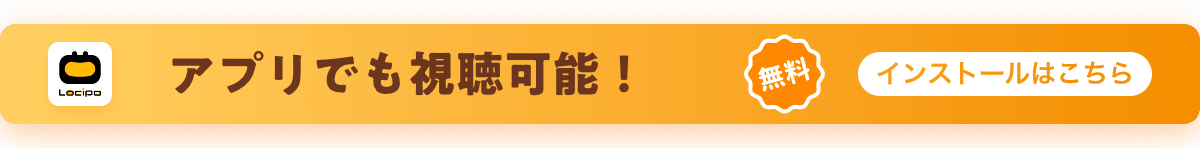カーボンニュートラルの実現のため、愛知県は次世代太陽電池の普及を目指します。次世代の太陽電池といわれる「ペロブスカイト太陽電池」の実装を目指す愛知県の推進協議会が5月30日に立ち上がりました。「ペロブスカイト太陽電池」はどのようなものか、実用化されると私たちの暮らしはどうなるのか、取材しました。
「軽い」「やわらかい」太陽電池

ペロブスカイト太陽電池は従来のシリコン太陽電池に比べ、軽くて柔軟なのが特徴です。愛知県はペロブスカイト太陽電池を普及させることで、二酸化炭素などの温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指します。
30日の会合には企業や自治体などから約180人が参加し、ペロブスカイト太陽電池の実装に向けたスケジュールなどについて意見交換を行いました。2025年度中に県の施設などでの実証実験を目指します。

ペロブスカイト太陽電池とはいったい、どんなものなのか、協議会で研究開発を担うアイシンの展示施設に行ってみました。
アイシン グリーンエネルギー開発室 遠山智之さん:
「こちらがペロブスカイト太陽電池です」
8つの太陽電池パネルが1つの回路にまとめられ、壁に貼りつけられていました。設置する前の状態を見せてもらうと、約2.5ミリメートルの薄さ。横向きに持つと、たわみました。曲げてしまっても破損することはありません。
歪んでも壊れにくい「ペロブスカイト結晶構造」

やわらかさの理由は、光を受けて電気をつくる発電層の素材にあります。
ペロブスカイト太陽電池の「ペロブスカイト」とは、結晶構造の一種です。ペロブスカイト結晶構造は歪んでも壊れにくい性質があり、この構造を持つ素材を使った発電層は、従来の太陽電池の発電層よりやわらかく、割れにくい特徴があります。
このため発電層を保護する素材も、シリコン太陽電池は主に強度が高いガラスを使っていたのに対し、ペロブスカイト太陽電池は軽くて柔軟性のあるフィルムなどで代用でき、薄さ、軽さ、やわらかさを実現しています。
大阪・関西万博で実装に向けた取り組みも

ペロブスカイト太陽電池はいま、さまざまなところで実用化に向けた取り組みが始まっています。JR東海は駅の電力の一部などをまかなおうと、防音壁に取り付けるパネルの開発を2025年1月に始めました。
大阪・関西万博ではスタッフのベストに取り付け、発電した電力で首元の扇風機を回すなどの実証実験も。
ペロブスカイト太陽電池でこの先、社会がどのように変わるのか。専門家に話を聞きました。
急に曲がったような屋根にも導入できる

あいちペロブスカイト太陽電池推進協議会の座長を務める愛知工業大学の雪田和人教授です。
――まずは、ペロブスカイト太陽電池は実用化されると私たちの暮らしはどのような風に変わるのでしょうか。
愛知工業大学 雪田和人教授:
「ペロブスカイト太陽電池は、軽くて薄い、軽くて曲がりやすい特徴を持っています。そうすると、今までシリコン型の太陽電池が設置できなかった場所にも設置できるようになります。
例えば、窓、壁、急に曲がったような屋根にも導入できるので、歩くとここにも、あそこにも太陽電池が設置されている、ような感覚がわかると思います」

――カーボンニュートラルの実現に一歩近づく、と。
「愛知県の計画で、これから再エネを中心に様々、導入していこうとの計画があるのですが、その計画に対して後押しするような感じで貢献できると思います」
――実用化まで、どれくらいの期間がかかりそうですか。
「議論の一部の話題としてありましたが、登山に例えるとちょうど5合目ぐらいだと言っていました。5合目までなら皆さんでたどり着けますが、そこから頂上を目指すとなると、さまざまな課題があります。
1人で登りきれないので、皆さんで下から押し上げよう、と。協議会のメンバーと作っている人たちが一体になって頂上を目指していこうと話しています」
――雪田さんが感じている課題は、具体的にはどんなことがあるのでしょうか。
「一般的に言われているのは、『チャンピオンデータ』という小さなナノセルだとシリコンを超えることができます。これから生産設備を整えて大型のパネルを作る、量産をする、シリコンと同じような寿命を持たせるとか。そうした量産化への課題は多くあると思います」